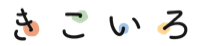79%の片耳難聴のある方が、両耳難聴の方と接する機会がほとんどない ?!
(Twitterの簡易アンケート結果より。96人回答)
- 「自分の聞こえについて、ちゃんと知ったのも、
自分以外の片耳難聴のある人とあったのも、最近のこと。
でも、片耳難聴の以外の聞こえにくい方のことも、よく知らないな…」
コラボ交流会は、片耳難聴のある人のこんな声から生まれました。
片耳難聴にとどまらず、様々な聞こえの特性、
また、聞こえだけでなく、多様な人の特性を知り合うことが
片耳難聴の当事者にとっても、助けやヒントになったり、
ひいては、誰にとっても過ごしやすい環境をつくっていくために大切なのではないかと思っています。
コラボ交流会第1弾「APD(Auditory Processing Disorder:聴覚情報処理障害)」に続き、
今回は、両耳難聴のある方との交流会を行いました。
開催概要
- 2022/03/13(日)@ビデオ通話ツールZoom
- 参加者
-片耳難聴のある方:6名(+きこいろ運営メンバー8名)
-両耳難聴のある方 :10名
-そのほかの聞こえの特性の方:1名
-両耳が聞こえる方(家族、支援関係者、友人知人など):9名 - 主催:きこいろ/共催:きこえカフェ
軽度難聴~重度難聴、補聴器ユーザーや人工内耳ユーザーなど
さまざまな聞こえの程度の方が集まりました。
この記事では、当日の様子の紹介と、聞こえに関する知識を補足してお伝えします。

■前半:エピソード発表
はじめに、お互いの聞こえについて概要を知る時間として
代表して1名ずつが体験談を紹介し、質疑応答を行う時間を設けました。
両耳難聴について
難聴という「目に見えにくい」点で、片耳難聴と共通しますが
両耳が聞こえない場合、より音を聞き取るのが難しいため、
補聴器機の使用や必要に応じてサポートを求めていく、というお話がありました。

話せる≠聞こえる
また、両耳が聞こえなければ、音声での発声ができないのではないか…
逆に、口頭で話しができているのであれば、耳も聞こえているのではないか…
そんな勘違いをされることもある、というお話がありました。
両耳が聞こえないと、周りの人の声も自分の声も聞き取れないため、どのような発声が正確かが分からないからです。
ただ実際には、発声の明瞭さで両耳難聴の程度は測れません。
見た目や発声で「聞こえていそう、大丈夫だろう」と一方的に思い込むのではなく、
一人一人にあったコミュニケーション方法を確かめることが大切です。
コミュニケーションの手段
イベント当日は「UDトーク」というリアルタイムで音声を文字化するツールを利用しました。
Zoom(ビデオ通話ツール)の画面上などに字幕を映すことができます。

視覚情報を使うと同時に、以下のようなコミュニケーションのポイントがあげられます。
聞き取りやすい話し方の例
- 一人一人、順番に話す。
複数の音が合わさると、聞き取りにくい。 - 静かなところで話す。
雑音があると、聞き取れなくなる。 - ゆっくり、はっきり話す。
一言一句ではなく文節ごと、怒鳴り声ではなく大きめな声。 - 顔の見える場所で話す。
話し手の顔・表情・口元を見ることでも、話している内容を理解するため。 - 話しかける前に、注意を引く。
相手の名前を呼んだり、手で合図する。
また、こちらが話しかけるときだけでなく、難聴のある人が発言しやすいようにすることも忘れずに。
「聴者(聞こえる人)の話を聞くのに集中しているうちに、次々と会話が進んでしまい、
自分の発言したいことがあっても、話すタイミングを逃してしまう」
「両耳が聞こえない人に、情報を伝えてくれるのは助かるが、
聞こえない人に意見を求めてもらえない」
そんな声もあります。
皆が参加し、コミュニケーションを取れるようにしましょう。
- * 字幕ツール「UDトーク」
- コミュニケーションの「UD=ユニバーサルデザイン(すべての人に使いやすい)」を支援するもの。
近年は、UDトークだけでなく、さまざまな音声認識機能を利用したツールが登場している。 - 詳細:https://info.roisinc.net/about/

■後半:グループでの交流タイム
後半は、8名程度に分かれてお話をしました。
困ること
●両耳難聴のある方からの声
「左右差があり、片方は重度難聴(90dB以上:大声でも聞こえない)、もう片方は中等度難聴(40dB~70dB:小さい声は聞こえない)。
コロナ渦前は自分が聞こえやすいように、職場の会議ではマイクを使用していた。
今は、感染対策のためマイクを回せないとなり、使えなくなった。
聞き取りにくいが、何度も聞き返せず、疲れてしまう」
●片耳難聴のある方からの声
「耳だけでなく、他の障害もあるが、見た目では分からないし、理解してもらいにくい。
そのため、人間関係に苦労することがある。
障害者手帳がどちらの障害でも貰える基準にないが、
周りの人から『障害者手帳はもらえないの?』と聞かれることがある」
伝えること
●両耳難聴のある方からの声
「両耳とも重度難聴。病院で、名前を呼ばれても聞こえないため、受付のときに伝えている。
説明などを代わりにスタッフがメモを取ってくれることもある。
スタッフ間で、引き継いで対応してくれることもあり助かる」
●片耳難聴のある方からの声
「片耳が中等度難聴。日常生活に大きな支障がないため、
周りの人に気づかれないし、伝えたとしても
片耳が聞こえる分、大丈夫と思われたり、忘れられてしまう。
そういうものだと割り切って、気持ちがくじけても、聞き返すようにしている」
旧優生保護法について
●片耳難聴のある方からの声
「最近、裁判があった『1948~96年に行われた、障害のある方に強制的に国が不妊手術を実施した』旧優生保護法について、どう思うか」
「生まれてきてはいけない命なんて絶対にないし、命の価値を他者や社会が決めてはいけない」
●両耳が聞こえる方からの声
「自分は、両耳が聞こえない親から生まれた子ども。
そのため、もし自分の親がこの手術を受けさせられていたら、自分はこの世にいなかったかも知れない。
当事者は、本人だけでなく、その子ども立場(CODA:コーダ)の人たちもいるのだという視点を持ってほしい」

感想
一部を紹介します。
両耳難聴のある方から
- 片耳難聴の合理的配慮について、
「電話のときはメモを」という根拠として、確かに良い耳がふさがっているからということに納得した。 - 片耳難聴でも、10人程度の会議の会話が聞き取れたり、
音の方向について、声質で誰が話しているか目安がつけられる方もいると知り、驚いた。
片耳難聴のある方から
- 「聴覚障害」と一括りではなく、
聴力の高低、難聴者になった時期、補聴器の使用の有無、
家族・友人との関係、学校/職場環境の違いなどによって
悩みも改善策も考え方も少しずつ違い、
グループトークで詳しくお話しできて良かった。 - 両耳難聴について詳しく知らなかったため、知るきっかけになった。
言語の明瞭さと難聴の程度は一致しないなど、
誤解しがちなことを知れて良かった。
両耳の聞こえる方などから
- 難聴のある方は、難聴を伝えたり、聞き返したり、
支援を何度もお願いしないといけないしんどさも抱えているのだと思った。 - 「聞こえなくても大丈夫な関係性」という言葉が新しい視点だった。
配慮をしなくて良いということではなく、
聞こえだけでなく人として信頼関係を結べるかどうかも大事なんだと感じた。
もっと知りたい方へ:参考文献
共催:きこえカフェ
聞こえの程度や原因を問わず、聞こえにくい方/聞き取りにくさをお持ちの方を対象に行う交流会。月1回程度、最近はオンラインにて開催。また当事者以外にも家族・友人知人・支援者・興味をお持ちの方も歓迎している。
▶詳細:https://sites.google.com/site/norikokatsuya/kikoecafe
企画主催:きこいろ
2019年に発足した日本で初めての片耳難聴(一側性難聴)の当事者を中心とした任意団体。「聞こえ方は、いろいろ」略して「きこいろ」。片耳難聴に関する情報発信、コミュニティ運営、啓発活動などを行う。
▶毎月、交流会や勉強会を開催中:https://kikoiro.com/about/cafe/
\ 活動を応援してくださる方 /
・ワンコイン募金
Zoom使用料や、今回の情報保障(UDトーク使用料)費用に充てさせていただきます。
・会員メンバー募集
会費1000円/年により、活動を支えていただいています。
・ボランティアメンバー募集
交流会のファシリテーターや、SNS運用のお手伝いをいただける方はお声掛けください。