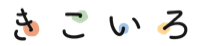症状
高度(70dB以上:大声で話しても聞こえない)の感音難聴(内耳以降に原因があるもの)発症から長期間(数年以上)経ってから、激しくグルグル回るようなめまい発作をくり返す。
めまい
- メニエール病と同じく、めまいは吐き気や嘔吐を伴う。
- 特別の誘因なく起こる。
- 横になってじっと休んでいてもめまいが続き、30分〜半日続く。
- 頻度は、1週間に数回〜年に数回と様々(一日に数回起こるものは、遅発性内リンパ水腫ではない)
聴覚症状
- すでに難聴側が原因であるケースでは、すでにほとんど聞こえない難聴のため、耳つまり・耳鳴り・難聴の変動はない。
- 高度難聴の耳が原因であるケースが多いが、稀に聞こえの良い方の耳(健側)が原因の耳となってめまい発作時を起こすことがある。
聞こえる側に原因があるときは、聴力の変動や耳なりが自覚できることもある。
経過・予後
生活改善と内服治療で効果がある症例もある。長期の経過は治療法の解明確立伴い、今後明らかになってくると思われる。
患者数
4,000〜5,000人
- 下記の要件に当てはまる場合は、難病法の「指定難病」の対象となり医療費助成の対象となる。
①遅発性内リンパ水腫の診断基準を満し、②両側の高度な前庭機能障害があり、③両側の難聴(40dB以上)で改善しない場合 - 「指定難病」とは下記の要件を満たすもので、治療の研究や患者の治療負担を国も支援する
①原因が明らかでない ②治療方法が確立していない ③稀な疾患 ④長期の療養を必要とする ⑤患者数が本邦において人口約0.1%程度に達しない ⑥客観的な診断基準が成立している
原因・病態

原因は不明。メニエール病と同じで、内耳の膜迷路(まくめいろ)の水ぶくれ(内リンパ水腫)による。
診断
- 問診(難聴の時期・めまいの様子)、めまい時の眼振所見、聴力検査などから診断する。
- めまい発作の原因の耳を明らかにするために、内リンパ水腫を検出するための検査が行われることもある。
グリセロールやフロセミドなどの利尿効果のある薬剤(点滴や注射、内服)の使用前後の聴力や前庭(バランス)機能の変化をみるもので、検査には2〜3時間かかる。めまいの専門病院で行っている。
気を付けること・治療
めまい発作時
メニエール病と同じ、やや暗めの部屋で横になって眠るのが一番です。
発作時に内服する薬(トラベルミンなど)が処方されていれば内服してひと眠りしましょう。吐き気止め(ナウゼリン・プリンペランなど)も一緒に飲むことがあります。だいたい2時間くらい眠ると楽になります。
発作のない時期
メニエール病と同じで予防の治療を行います。
規則正しい生活(充分な睡眠、適度な運動)や、内リンパ水腫を改善する利尿剤(イソバイドや五苓散など)内服を行います。
発作のコントロールが難しいとき
メニエール病と同じように、中耳加圧器治療(ちゅうじかあつきちりょう)が保険適応になりました。
原因が難聴側の耳であれば、アミノグリコシド系薬剤の鼓室注入(こしつちゅうにゅう)や前庭神経切断術(ぜんていしんけいせつだんじゅつ)により前庭(バランス)機能を破壊し、めまい発作を起こらないようにするケースもあります。ただし、聞こえの良い方の前庭機能が正常でないとふらつきが持続して生活に支障が出るため、慎重に検査を行い判断する必要があります。
- 中耳加圧器治療
専用の耳栓をメニエール病の耳に挿入するため、鼓膜に孔があいている方は使用できません。病院から中耳加圧器をレンタルして 1回3分間、1日2回毎日自宅で治療を行います。治療期間中はめまいの記録を付け、4週に1回耳鼻科医の診察を受ける必要があります。 - アミノグリコシド系薬剤の鼓室注入
鼓膜切開や鼓膜チューブを挿入して、内耳の前庭機能を破壊する薬剤(ゲンタマイシンなど)を中耳に注入します。めまい発作がなくなるまで何度か注入します。
激しいめまい発作は起こらなくなりますが、注入した側の前庭(バランス)機能が失われるので、慢性のふらつきが続くことがあります。 - 前庭神経切断術
バランスの神経前庭神経を切断して、内リンパ水腫の発作が頭(中枢)に伝わらないようにします。手術は開頭手術になります。
ほぼ100%めまい発作は起こらなくなりますが、慢性のふらつきが続くことがあります。