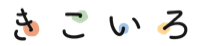片耳難聴者が工夫していること
子どもの頃から片耳難聴のある4名の方に、聞こえにくい場面でどのような工夫をしているかインタビューをしてみました1)。
自己努力系の対応
- 聞こえやすい席や立ち位置に移動する、キープする。
- 話している人の方に顔(耳)を傾ける。
- 話している人の口元をよく見る。
- こんなこと話しているのかなと一生懸命考える。
- 声がしたらキョロキョロしてみる。
- 音の場所が分からない時は、耳を傾けて移動してみる。
他者依頼系の対応
- 「こっちの耳が聞こえない」と伝えて、場所を移動させてもらう。
- 「今は聞こえない」と言って、話は後にしてもらう。
上の6つは「自己努力系の対応」、下の2つを「他者依頼系の対応」と勝手に命名してみました。
自己努力系の対応
「自己努力系の対応」では、やはり「聞こえやすい位置のキープ」は片耳難聴あるあるですね。
難聴側に人が来ないように、聞こえる側に人が来るようにするといった場所取りが、飲食店や会議など複数の人で席につくときや、隣同士で並んで歩くときなどに必要です。
耳を傾けたり、口元をよく見たり、何を話しているのか推測したり、うるさい場所などの聞こえにくいときには、集中して頭フル回転して疲れる…という方も。
音がどこからするのか分からないとき、遠くから名前を呼ばれたときなど、とにかく振り返ったりキョロキョロして目で見て確認したり、携帯電話の着信音などは耳を傾けながら移動してみて、音が大きくなる場所を探すこともありますよね。

他者依頼系の対応
「他者依頼系の対応」では、自己努力ではどうしても聞こえやすい位置をキープできないときには、周りに移動させてもらえるようお願いすることもあるかと思います。
また、周りがうるさすぎてどうしようもないときには「今は聞こえない」とハッキリ伝え、後で話して貰うという方もいましたが、これは相手と関係性も大事です。
「他者依頼系の対応」をする前提として、相手に自分の難聴について開示(カミングアウト)する必要があります。 この難聴の開示(カミングアウト)について、次のページで詳しくお話しします。