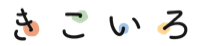公募企画に、560件以上ものご応募をいただきました。
片耳難聴を持つご本人以外からのご応募が多く、
クリエィティブ系の学校などの授業の一環として取り組んでくださった方、
周囲に片耳難聴の方がいる方、
ご自身に片耳難聴ではないけれど持病を持っている人など、
難聴の有無にかかわらず、
広く多くの方に考えていただくことができました。
寄せられたメッセージの一例
- 私は、片耳難聴の方には会ったことがありません。しかし、意識できていないだけで、すれ違ったことぐらいはあるのではないかとマークを考えながら思いました。
- 片耳難聴の方とは違う病気を持っております。ですが「見た目では分からない病気」という意味では共感し、応募しました。
- 昔、片耳が聞こえにくい友人がいたことを思い出しました。
苦労している様子は分かりませんでしたが、実は陰で大変だったこともあったんだろうなと思いました。
【2/28 リリース】
片耳難聴のオリジナルマークは、こちらより
素材データを無償提供、グッズを販売しています。
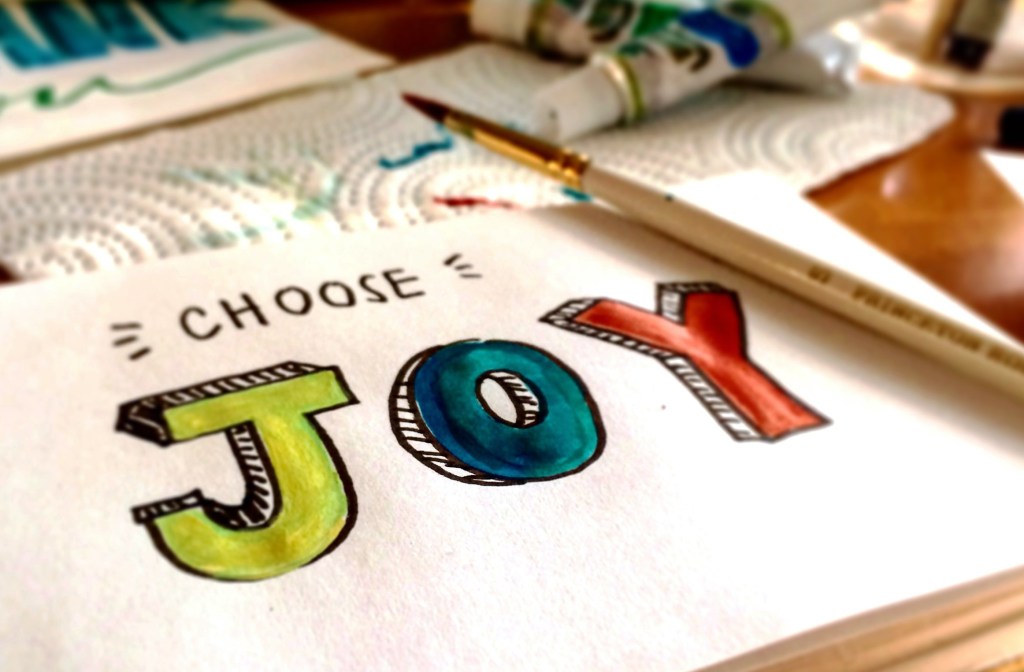
改めて、企画概要についてご説明します。
企画概要
企画プロセス
外見では分かりづらい、聞こえづらさ。
「忘れられないために、目印があったらいいのかな」
そんな声をきっかけにはじまった企画です。
片耳難聴を可視化するマークがあれば、困りごとが解消されるかもしれません。
しかし、先のコラムで紹介したように「ヘルプマーク」や「耳マーク」を始めとして、
福祉や聞こえに関するマークが既に多数存在しています。

「なぜ、きこいろが片耳難聴のマークをつくる必要があるのか」
約150名からのアンケートや企画メンバーで議論を重ねる中で、
いくつか見えたことがありました。
聞こえ方は、いろいろ
ひとくちに片耳難聴といっても、聞こえ方はいろいろ。
感じ方や、困ること、悩みも一様ではありません。
たとえば、
通りすがりの人のように、コミュニケーションをとらない人にまで常に配慮を求める必要はないと思う人もいます。
普段のコミュニケーションでも、一対一や静かな場所では、さほど問題がない場面もあります。
ヘルプマークのような強くサポートを求めるような既存のシンボルマークが、自分にはしっくりこないと感じる方もいます。
片耳難聴の聞こえ、付き合い方もさまざまだからこそ、
既存にはない、多くの人に理解や援助を強く求めないマークがあってもいいのかもしれない。
また、そうした「片耳難聴との付き合い方」を自分で選ぶことが大切だと考えます。
マークを自分で選ぶ、あるいは使わないと選ぶ過程がそのきっかけになりうる、と考えました。

好みも、いろいろ
片耳難聴を持つ人、一人一人の好みも当然異なります。
持ち物は、自分の一部。
「私はこれがいい」「僕はこれがいい」と
一人一人のセンスや生活シーンに合わせて選べることを大切にしたいと思いました。
そこで、きこいろは
ファッションツールのようなハイセンスなマークを、
使いたい人のニーズによって選べるように複数つくることにしたのです。
マークの役割
マークの機能・使用イメージ
- 片耳難聴を表明するチャーム
:自分のために使いたい方 - 自己開示のきっかけの補助ツール
:片耳難聴を開示している身近な人との間で使いたい方
:片耳難聴を知っている身近な人が思い出すヒントとして
困りごとは誰しもあり、特別なことではないと知っているのに、
それを切り出すことの難しさを私たちは知っています。
自分から伝えなければ分かって貰えないのも、たしかです。
でも、改まって話をするには勇気がいったり、どう伝えたらいいんだろうと考えているうちに、困りごとを独りで抱え込んでしまうこともあります。
そんな時、マークがあったら
「ひとりじゃない、片耳難聴の仲間がいる」と思い出す勇気になったり、
「これはなんだろう?」と見た人の興味を引いたり、
「このマークって、実は片耳で聞いているのを表しているんだ」と伝えたり、
コミュニケーションの扉を開くツールとなるかもしれません。
マークが架け橋となって、
片耳難聴であることを伝えたい相手と、相互に理解を深めていくことができたらいいなと思っています。
制作方法・マーク紹介
バリエーションに富むマークを作成するために、3つの方法でマークを作成しました。
詳しくは、各ページをご覧ください!
1. 公募作品
2. 片耳難聴キクチさんによる制作
3. きこいろPJメンバー企画担当者作品
- 「伝える」をサポートするツール、リーフレットはこちらから。