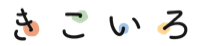「音楽を聞くことで、難聴のリスクを高めるのではないか」
といったご相談がしばしば寄せられます。
ヘッドホンやイヤホンを使っての音楽鑑賞だけでなく、
吹奏楽やマーチングといった演奏活動での音量も
片耳難聴を持つご本人や周りの方々にとって、気になる場合があるかと思います。
この記事では、音楽を楽しむ場面に注目して
聞こえている耳を大切に音楽と付き合うヒントを詳しくみていきます。
1. 生で音楽を楽しむ時

楽器を演奏したり、歌ったり、
時にはコンサートやライブへ行くこともあります。
このように、生で音楽を楽しむ時にはどのような点に注意すれば良いのでしょうか。
アコースティックな音楽の場合
クラシック作品などの、アンプ(音の増幅器)を用いないアコースティックな音楽では
アマチュアや観客に、難聴がみられたというケースはありません。
そのため、一般的なプレーヤーやリスナーが
極端に心配する必要はないといえるでしょう。
一方で、日々ハードに練習し、よくステージに立つプロの演奏者は
騒音性難聴になることがあるという報告もあります1)。
実際に、交響曲作品のうち10分を切り出して騒音レベルを測定した結果、
パートの位置によっては、騒音性難聴防止のため対策が推奨される
85dB (A) を越えていたというデータもあります2)。
そうした背景から、プロの楽団の中には
騒音性難聴防止のため対策を始めた所もあります。
しかし、長年ステージに立つプロの演奏者でも、聴力が正常な人は多く3)、
アコースティックな音楽の音は、耳障りな騒音とは違った作用を持つと考えられています。

アンプを使った音楽の場合
ライブなど、特に狭い会場でアンプを使った音楽は大音量になります。
そのような所では、ゆっくり進行する騒音性難聴のリスクに加えて、
音響外傷* が起こることがあり、注意が必要です。
これは音源に近い演奏者だけでなく、観客にもいえることです4)。
予防のためには、下記のようなことに気を付けると良いでしょう。
騒音性難聴や音響外傷の予防ポイント
- スピーカーの近くを避ける
- ライブの後は静かなところで十分に耳を休ませる
- ライブ用のイヤープロテクター / イヤープラグを使用する
イヤープロテクター / イヤープラグとは、
聞こえている音のバランスを変えずに、音量を小さくするというものです。
通常の耳栓では、低音域に比べ、
高音域の音が小さくなりすぎるため、こもった感じに聞こえます。
イヤープロテクター / イヤープラグは、
着けていても自然な聴こえで音楽を楽しめます。
イヤープロテクター / イヤープラグには
耳型を取ってオーダーメイドで作成する本格的なもの
Musician’s Ear Plugs
CDショップなどでお手軽に買えるもの
Music
ファッション性の高いもの
Loop
と様々な製品があります。
- * 音響外傷:
詳細な罹患率は不明。
大きな音を聞いた直後から数時間のうちに、難聴や耳鳴りや耳閉感を自覚する。
一側性あるいは両側性。一過性のめまいを伴う事がある。耳痛は伴わない。
発症早期では突発性難聴に準じた治療を行う3)。 - 爆発音など予期しない音による聴力低下を「(急性)音響外傷」、
音楽など意図して聞いた音による聴力低下を「(急性)音響性難聴」と区別することもある。
2. 音楽プレーヤーで聴く時

最近、大音量で音楽を聞くことにより難聴のリスクが高まるとして、
いわゆる「ヘッドホン難聴 / イヤホン難聴」が注目されています。
WHO(世界保健機構)によると、ヘッドホンで音楽を大音量 / 長時間聴くことで、
11億人の若者が騒音性難聴のリスクにさらされていると警告しています5)。
音楽を聴く時はどのくらいの音量 / 時間が良いのでしょうか
一つの目安として、60 / 60ルールがあります。
- ボリュームを再生機器のおよそ60%にとどめる
- 一度に聴く時間を60分(1時間)以内にする
音楽を聴いた後は、10分ほど耳を休ませます。
また、周りが騒がしい所ではボリュームを上げがちです。
一定以上の音量にならないリミッター機能を活用すると良いでしょう。
そのような所では、外部の雑音を軽減する仕組みの
「ノイズキャンセリングヘッドホン」を使うことで、
ボリュームを抑えたまま快適に聴くことができます。
(詳しくは:片耳難聴と音楽)
もし耳鳴や耳閉感など、何かしら違和感があったときは、
放置せずに、耳鼻咽喉科専門医(騒音性難聴担当医)に相談しましょう。

この記事では音楽を楽しむ場面に注目して
聞こえている耳を大切にするヒントをご紹介しました。
音楽を楽しむ際の参考になれば幸いです。
出典・文献
- Pouryaghoub, G., Mehrdad, R., Pourhosein, S.: Noise-induced hearing loss among professional musicians. Journal of Occupational Health, 59(1), 33–37 (2017)
- 青野正二,黒田克典,瀧浪弘章,他:TTSから見た楽器の音及び管弦楽が演奏者の聴力に与える影響. 日本音響学会誌, 56(2), 105–114 (2000)
- Karlsson, K., Lundquist, P. G., Olaussen, T.: The Hearing of Symphony Orchestra Musicians. Scandinavian Audiology, 12(4), 257–264 (1983)
- 村井和夫:音楽と聴覚障害. 耳鼻咽喉科展望, 42(2), 112–124 (1999)
- World Health Organization “Make Listening Safe” (2020/11/6)