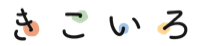1.先天性の場合
新生児聴覚スクリーニングの普及によって、
乳児期に片耳難聴のお子さんが毎年1,000人余り発見されるようになりました1)。
頻度は約0.1%(約1,000人に1人)です。
その原因として一番多いのは、
蝸牛神経(「かぎゅうしんけい」きこえに関する神経)の低形成です。
次に多いのは、先天性サイトメガロウイルス(CMV)感染によるものです。
先天性サイトメガロウイルス(cytomegalovirus : CMV)感染
出生時から片耳難聴のこともありますが、両耳難聴のこともあります。
また、幼小児期になってから難聴が生じる遅発性の場合や進行性の場合もあります。
その他には、
蝸牛神経低形成以外の先天性内耳(ないじ)形成不全によるもの、
内耳(蝸牛)とその奥の蝸牛神経の間において音の情報を伝達できないオーディトリーニューロパチー(auditory neuropathy spectrum disorder : ANSD)の片耳タイプ、
ワールデンブルグ症候群の片耳タイプ、
先天性風疹症候群の片耳タイプ、
先天性中耳形成不全の片耳タイプ(小耳症や外耳道閉鎖/狭窄を伴う場合も伴わない場合もある)
などがありますが、
原因不明の場合も多くみられます。

2.幼小児期発症の場合
子どもの頃の片耳難聴の原因として、
CMV感染や先天性風疹症候群で遅発性、
進行性に発症した場合の他に、
ムンプス(おたふくかぜ)によるムンプス難聴があります。
2015~2016年のムンプス流行時に、
日本耳鼻咽喉科学会で全国調査を行ったところ、359例がムンプス難聴と診断され、
このうち95.5%が片耳難聴、4.5%が両耳難聴だったと報告2)されています。
そのうち、片耳難聴の91%は高度・重度(大声でも聞き取れない・ほとんど聞き取れない)難聴だったとのことです。
この調査によると、発症年齢は
就学前と30歳代の子育て世代にピークが認められていますが、
子どもがムンプスにかかり、予防接種を受けていない養育者が二次感染を起こしていることを示しているのではないかと考察されています。

3.成人発症の場合
突発性難聴、
メニエール病、
急性低音障害型感音難聴、
慢性中耳炎、
真珠腫性中耳炎(しんじゅしゅせいちゅうじえん)、
聴神経腫瘍などが挙げられますが、
その他、外リンパ瘻(がいりんぱろう)、
機能性難聴、
ムンプス難聴など、原因は多彩です。
先天性(若年性)片耳ろう(重度難聴)の方の中には、
「遅発性内リンパ水腫」という、数年~数十年経ってからメニエール病のような回転性のめまいが生じることがあります。
遅発性内リンパ水腫(ちはつせいないりんぱすいしゅ)
先行する片耳または両耳の高度感音難聴に、
数年~数十年経ってから、
メニエール病のような回転性のめまい発作を生じるものとされています。
先天性(若年性)片耳ろう(重度難聴)の方の場合は、
同側型と対側型があります。
- 同側型
難聴側に内リンパ水腫が生じた場合で、回転性めまいのみ - 対側型
難聴側と反対側の耳に内リンパ水腫が生じた場合で、回転性めまいと良聴耳の聴力が変動
対側型は、たまたま良聴耳にメニエール病が生じた可能性を否定できないため、
同側型のみが、診断の要件をすべて満たす場合に
「難病法」における医療費助成の対象となる指定難病となっています。
参考文献
- 日耳鼻福祉医療・乳幼児委員会:平成29年度難聴が疑われて乳幼児精密聴力検査機関を受診した0歳児および1歳児、2歳児の社会的調査.日耳鼻121:1033-1040,2018
- 日耳鼻福祉医療・乳幼児委員会:2015~2016年のムンプス流行時に発症したムンプス難聴症例の全国調査.日耳鼻121:1173-1180,2018